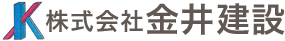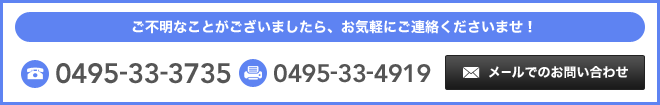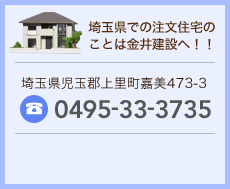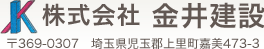建前、上棟式、木遣り
上棟式とは、建物の新築の際に行われる神道の祭祀である。棟上げ(むねあげ)、建前(たてまえ)、建舞(たてまい)ともいいます。
竣工後も建物が無事であるよう願って行われるもので、通常、柱・棟・梁などの基本構造が完成して棟木を上げるときに行われる。式の方法や次第には神社の祭祀のような規定はなく、地域による差異もあります。屋上に祭壇を設けそこで祭祀を行うものや、祭壇のみ屋上に設けて祭祀は地上で行うもの、祭壇も祭祀も地上のものの区別もある。神社本庁では「諸祭式要鋼」で上棟式の基準を示しています。それによれば、祭神は屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)、屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)、手置帆負命(たおきほおいのみこと)、彦狭知命(ひこさしりのみこと)および当地の産土神であります。まず、他の祭祀と同様に修祓・降神・献饌・祝詞奏上が行われます。次に、上棟式特有の儀礼として、曳綱の儀(棟木を曳き上げる)、槌打の儀(棟木を棟に打ちつける)、 散餅銭の儀(餅や銭貨を撒く)が行われる。最後に、他の祭祀と同様に拝礼・撤饌・昇神・直会(なおらい)が行われます。
建前、棟上とは普請を生業にする職人がいる地域では、棟梁(大工)が中心になり大工の作成した番付表(組み立て手順書の様な物)を見て鳶職が軸組みの組み立てを行い一番高い棟木を設置する一連の作業を指す。その最後の作業からその後の儀式を上棟式、棟上式という。
鉄筋コンクリート造のビルの場合でも、主要な構造ができあがった時期に行われることがある。
上棟式の由来
それは、こんな話しです。
昔、とても高名な棟梁がいました。その棟梁が明日が建前という前の晩になって、自分のミスに気づきます。玄関の柱を短く刻んでしまって、どう考えても直せない。棟梁は、自分 の未熟さに死のうと考えます。
それを見た棟梁の奥さんが、自分が代わりに死んでも良いとまで思い、棟梁に酒を飲ませて寝かしつけ、寝ないで考えたのが、枡(マス)を使って補修する方法でした。
翌朝目覚めた棟梁は、奥さんの差し出した枡を受け取ると、「わかった!」と言い、柱の足りない分を補い、事なきを得たのです。ところ が、自分の恥が表に出るのを恐れた棟梁は、自分の表向きの見栄や意地のために、奥さんを殺してしまいました。
殺してから棟梁は、自分の犯した罪を悔い、未来永劫、弔うと心に誓い女 の七つ道具(口紅・鏡・櫛・かんざし・おしろい・こうがい・かつら)を棟の上に飾って供養したと言うのが始まりで、建前の儀式となったそうです。
「タテマエ」にこだわるあまり妻を殺してしまった男の見栄や意地に、 「ホンネ」で応じた女の悲話が「本音と建前」の語源となったと言われています。とても悲しい話しですね。
建前&棟上げ動画
上棟式動画
木遣り
建築した家の家門長久を祈って心清らかに唄うもので、古くから施主様に対する何よりのお祝いだったのです。最近は正式に唄える人がほとんどなくなったことは残念なことです。施主様には何を歌っているか歌詞が分からないのが現実ですが、独特の音程と周りの人の発声も耳を傾けてしまいます。私達は古くからの教えや風習を多くの人に話しかけたいと思います。
木遣りの由来
木遣り(きやり)は、労働歌の一つ。1202年(建仁2年)に 栄西上人が重いものを引き揚げる時に掛けさせた掛け声が起こりだとされる事がある。掛け声が時代の流れにより歌へ変化し、江戸鳶がだんだん数を増やした江戸風を広めていった。鳶口を使って木材や丸太や原木などを動かすことを「木を遣り廻す」たんに「木遣り」ともいう。このことから仕事をこなすこと遣り回しともいい、鳶職や大工などが、 主役であった祭りの山車などの移動操作なども遣り回しと言う。鳶口を使って木を遣り回す時に、唄われたものが木遣り唄になり、現在の鳶職に受け継がれている。
主役であった祭りの山車などの移動操作なども遣り回しと言う。鳶口を使って木を遣り回す時に、唄われたものが木遣り唄になり、現在の鳶職に受け継がれている。
木遣り(きやり)は、労働歌の一つ。1202年(建仁2年)に 栄西上人が重いものを引き揚げる時に掛けさせた掛け声が起こりだとされる事がある。掛け声が時代の流れにより歌へ変化し、江戸鳶がだんだん数を増やした江戸風を広めていった。鳶口を使って木材や丸太や原木などを動かすことを「木を遣り廻す」たんに「木遣り」ともいう。このことから仕事をこなすこと遣り回しともいい、鳶職や大工などが、
 主役であった祭りの山車などの移動操作なども遣り回しと言う。鳶口を使って木を遣り回す時に、唄われたものが木遣り唄になり、現在の鳶職に受け継がれている。
主役であった祭りの山車などの移動操作なども遣り回しと言う。鳶口を使って木を遣り回す時に、唄われたものが木遣り唄になり、現在の鳶職に受け継がれている。上棟式木遣り動画